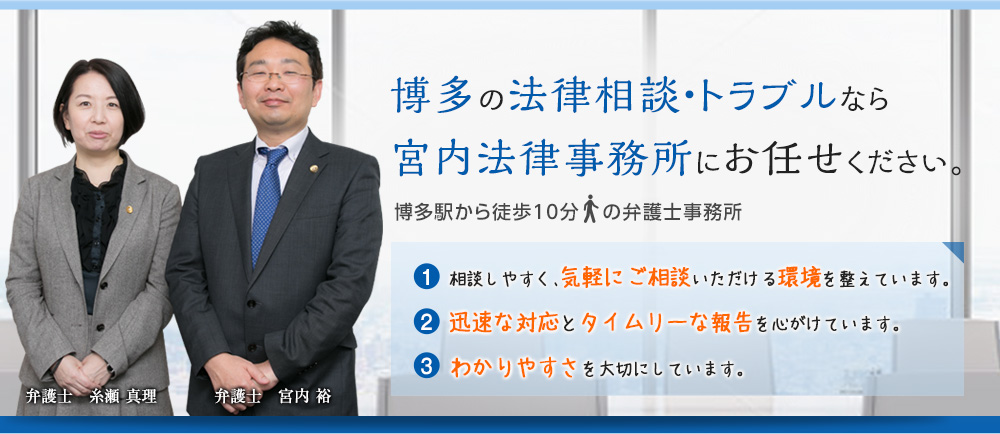中小企業が融資を受ける際、経営者が個人として連帯保証を求められるのが従来の常識でした。
しかし近年は、金融庁や中小企業庁の後押しもあり、保証を外しやすくする制度が整備され、金融機関の対応も進んできています。今回は、経営者保証を外すための代表的な3つのルートを整理しました。
1.日本政策金融公庫(公庫)の制度を活用する
まず押さえたいのが、日本政策金融公庫です。公庫には、一定の条件を満たすと代表者保証を求めない4つの制度があります。
- 新たに事業を始める方または事業開始後2期以内の方への融資 ●生活衛生改善貸付
- 小規模事業者経営改善資金融資(マル経) ●経営者保証免除特例制度
既存の融資の経営者保証を外す場合は、これらの制度を使って新しい融資を受け、既存借入を借り換える形が一般的です。制度の要件を満たすことが前提となり、審査には時間がかかる場合もあります。
早めの準備と、経営計画や返済可能性を示す資料づくりが重要です。
2.信用保証協会の保証制度を活用する
信用保証協会を利用した融資の中で、経営者保証を求めない制度を活用する方法があります。
代表的な制度は次の7つです。
- 創業融資制度(創業5年以内) ●事業者選択型経営者保証非提供制度
- プロパー融資借換特別保証制度 ●事業承継特別保証制度
- 金融機関関連型 ●財務要件型 ●担保充足型
信用保証協会は審査基準が比較的明確で、財務内容・法人と個人の分離・資本の充実度などを重視します。たとえば役員貸付の整理、決算書の精度向上、月次管理体制の整備など、制度の要件に合わせて準備を整えることが成功のカギです。
3.プロパー融資で金融機関と直接交渉する
信用保証協会を介さず金融機関が自らリスクを取る「プロパー融資」です。これは金融機関ごとの判断によって大きく結果が変わります。
重要なのは、担当者だけでなく本部の承認を意識した資料づくりです。
担当者が前向きでも、本部が納得しなければ保証解除は認められません。
経営計画や資金繰り表を添え、「なぜ保証なしでも問題ないのか」を数字とストーリーで説明することが必要となります。
4.ルート選びこそ成功のカギ
「日本政策金融公庫」「信用保証協会」「プロパー融資」という3つの主要ルートを理解し、自社に合った道を早めに選ぶことが保証解除成功の第一歩です。選び方を誤ると準備や交渉の方向がずれ、時間と労力を無駄にする恐れがあります。保証解除には制度知識だけでなく金融機関との交渉や資料づくりのノウハウも必要です。独力より専門家の助言を受けることで成功の可能性が大きく高まるため、初めての方は早い段階で専門家に相談されることをお勧めします。